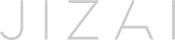本で拓けたアメリカ留学
――「本」は次へ飛び出すきっかけを与えてくれると。
篠崎英明氏:
私自身も多くの本との出会いによって、世界が拓けてきました。高校生の頃、渋谷の紀伊國屋で偶然『留学ジャーナル』を手に取ったのがきっかけで、毎日の単調な高校生活に飽きていた私は、「よし、行こう!」と決めてしまって、ニューヨーク州立高校へ1年間留学しました。
留学の前に英語や作文、面接などの試験があったのですが、それまで全く海外経験もなく、英語も別段得意という訳ではなかったのですが、なんとか受かりました。考えてみたら、それが一番最初の面接らしい面接だったかもしれませんね。
――アメリカでの留学生活はいかがでしたか。
篠崎英明氏:
ニューヨークと言っても、いわゆるマンハッタンではなく、バスが1日に1本か2本しか来ないような田舎でした。英語も一生懸命勉強しなければと思ったのですが、すぐに諦めて、チアリーダーに目が向かいました。
――何をしたのですか(笑)。
篠崎英明氏:
チアリーダーの華やかさに憧れて、バスケットボールのクラブに入りました。残念ながらバスケットボールの素質はなかったようですが、アメリカではシーズンごとにフィーチャーされるスポーツがあって、もともとやっていた陸上競技で先生の目に留まり、花が咲きました。
幼稚園からやっていたピアノも、少しばかり日の目を見ました。中学生の頃にはジャズとクラシック両方やっていたのですが、向こうの高校の音楽の先生に「お前、コンクールがあるから出てみろ」なんておだてられて、結局勝ち抜いて田舎のラジオで放送されたりしました。
そのままアメリカの大学へ進学も考えていて、高校の先生と一緒に大学を見学していました。試験の手配も先生がしてくださったのですが、私が試験日を間違えてしまいました。
「(留学試験に)受かる訳がない」と高を括っていた両親も、実際に留学して、さらにそのまま残ると言い出した息子にハラハラしていたのかもしれません。「戻ってこい」と言うので、とりあえず日本に戻って来ました。
チャレンジなくして成果なし
――「行ってみた、やってみた」ことが、様々な成果に繋がります。

篠崎英明氏:
それはこれからお話しする私の転職活動においても同じことが起こりました。今までの情報だけで判断してしまっては、広がるものも広がりません。常識を少し疑ってみて進むことで、新たな世界が広がります。
アメリカから帰国後、時間があったので、車の免許を取ったり、親から何とか買ってもらった中古の車で学校に乗り付けたりと、ずいぶんと自由に過ごしていました。大学では、パブでウェイターのアルバイトをしていました。その頃は髪も金髪で、毎日楽しくて、その日その日を楽しく過ごしていました。ある日、その様子を見かねた高校時代の友人から、「地に足の着いた仕事を」と、短時間正社員の形で国際電話のオペレーターの仕事を紹介してもらいました。結局それからは卒業までずっと、その仕事を勤めあげました。学生の割に高額だったアルバイト代は、すべて車に消えていましたが……(笑)。
大学の4年ぐらいになると、急にパイロットになりたいと思い、予備校に通いイチから勉強し直したり、彷徨っていましたね。結局パイロットの夢は、希望する会社がその年に採用がないことがわかって、諦めました。
――いよいよ年貢の納め時です。
篠崎英明氏:
そろそろ働かないと、と普通の就職活動をしようとしたところで、はじめて「何にも準備してない、何もわからない自分」に気がつきました。社会もなにもわかっていなかったので、とりあえず大手企業にと安直にも考えてしまい、商社を受けます。
商社の面接では、大学名で呼ばれました。「東京大学の何々さん」と話す面接官は、ニコニコと楽しそうでしたが、私が呼ばれた時は、真逆の反応で……(笑)。留学の話も、気にかけてもらえず、なんとかできないかと友人に相談したところ、「教授の推薦状」というのが効力があると聞いて、どこまで勉強していたか怪しいものでしたがドイツ語とドイツ経営学をとっていた私は、ゼミの先生に推薦状を書いて頂き、ヤナセを受けることに。
そこの面接官はとても柔らかな人で、「ああ、この会社はいい会社かもしれない」と思って(笑)、ところが筆記試験でまさかの寝坊をしてしまいます。毎晩夜中に遊んでいた私は、見事に寝過ごしてしまったのです。
開始時間には間に合いませんでしたが、とりあえず受けても良いということになりました。希望者には英会話の試験があり、このままでは確実に落ちてしまうと考えていた私は、まっさきに手を挙げました。留学をしていたのでペラペラと話しますと、大逆転です。おかげで内定を頂きヤナセに就職します。
――ものすごい就職活動劇ですね。
篠崎英明氏:
そこからまだ続くんです(笑)。ヤナセでは雪上車の営業に携わっていたのですが、冬はほとんどスキー場回りで、真っ白な景色を見ながらふと、「ベンツを売るだけではなく乗りたい」と思い始めました。25歳ぐらいの頃ですね。
それだったらもう独立して会社でもやらなきゃいけないなと思い、起業するための資金の相談のために、なぜか銀行の人を家に呼んだりしていました。本当に怖いもの知らずで、来てくれた銀行の人からは、「まずはご両親に相談すべきです」なんて言われてしまって。
まずは手に職をつけようと、知り合いの美容師の所へ丁稚奉公に出ます。当時男性の美容師は少なく、面白そうだったのでその世界に進みます。昼間はシャンプーをしながら現場で修行して、夜は山野美容学校へ通っていました。
せっかく就職できたヤナセを「辞める。そして美容師になる」と言った時は、まわりからあきられました。学校では、山野愛子ジェーンさん(現:山野美容専門学校校長)が同級生でした。ほかにも、当時一緒だった菅野という同級生は、ハリウッドで美容師として活躍しています。そこで美容師免許を取って、登戸のひとつ先の宿河原という場所で、美容院を開業しました。
パーマ液やヘアダイで手が荒れながらも、手伝ってくれた同級生の菅野と、楽しくやっていました。ところが多店舗展開を目論んでいた頃、手に入れるはずだった物件がポシャってしまって、外は雨で、客は誰もいなくて一人で店にいて、「このままどうなっちゃうんだろう、俺は」という思いにかられてしまいました。
――ボロボロの手を見ながら。
篠崎英明氏:
心もボロボロになりかけました。今は20代後半で若いから何とかなるけど、これが40歳になったら女性も、気持ち悪がるよと思った時に、ちょっと気弱になったんですね。その時に、ソシエワールドがエステティックのエリアマネージャーを募集していて、たまたま求人を見て応募し、あっさりと転職してしまいました。
そこでは店舗管理をするものとばかり思っていたら、社長からのお達しで、なぜか人事部門を担当することになりました。ちょうどバブルの後半で、まだ業界も元気な頃で、店舗展開のための人材が不足していました。そこからようやく今の、人事の世界へと話は繋がっていきます。