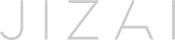伝統の“音”を日常に
上川宗達B氏:
日伸貴金属のある台東区三筋は、御徒町から蔵前のあいだを指す「徒蔵(カチクラ)」と言われていて、その昔、職人たちは物流の中心である日本橋に納めに行く前に、この付近の道を通っていました。それでこの地域には伝統工芸に関連した色々な工房があるのです。ここで、父であり師匠の上川宗照と三男一女の江戸っ子一家が同じ工房(日伸貴金属)で仕事をしています。江戸から東京に脈々と受け継がれてきた技巧を基に、新しいセンスを融合させた次世代の伝統工芸を目指し、日々の研鑽に努めています。
伝統工芸一家で育った私は、幼い頃からこの世界に進むと決めていました。跡を継ぐように言われたことは一度もありませんでしたが、働く父の背中を見て自然に憧れを抱くようになったのです。私は四人兄弟の末っ子でしたが、母は常に父の素晴らしさを説いてくれていました。そうした母の言葉にも大きな影響を受けたと思います。家の一階が仕事場で、二階部分に家族が住んでいましたが、父が銀を叩いたり削ったりする音が日常でした。その日常の延長で始まりました。
この世界に入ったばかりの頃は、銀をたたくよりも、まず道具づくりからでした。それぞれの作品に応じて、道具を作っていきます。しばらく道具づくりを覚えながら、徐々にまわりをまねながら作品づくりを始めました。最初は自分が身につけるアクセサリーに挑戦することにしました。それを見た友人から製作を依頼され、徐々に人に感謝される“ものづくり”の喜びを覚えていきました。
伝統工芸一家の挑戦

上川宗達B氏:
東京銀器は、昔、分業制でした。まず板を作る人がいて。形を作る「へらしぼり屋さん」に、轆轤(ろくろ)を使い、削ったり板を抜いたりする「ひきもの屋さん」。それから「みがく屋さん」と、溶接したりする「まとめ屋さん」など、たくさんの職人さんがいました。ある時、父から「自分のところで、全部できるようにしよう。時間をかければ何とかなる。職人さんのところへ行って、見て覚えてこい。わからなかったら、何度でも見てこい」と言われました。人数減少に伴う納期の遅れの発生。その結果、仕事がなくなる、ということを見越しての決断だったと思います。
真ん中の兄は、へらしぼり屋さんのところへ行っていましたし、私も削る刃物を作る工程や、木型作りを見て学びました。組合内の青年部も、今は10人くらいしかいませんし、その中でも私は一番若手。あと10年経つと、無くなってしまう技術もあるかもしれません。そういった技術をいかに吸収し、継承していくか。
金春流(こんぱるりゅう)の山井綱雄先生は「僕は一瞬の中で演技する。でも上川さんのところはそれがずっと続くものだ」とおっしゃっていました。常に挑戦し続けながら、後の世にも恥ずかしくないものを作らなくてはいけません。